2025.06.17 紹介の基本 マーケティングノウハウ
Z世代マーケティングの新常識:広告が刺さらない3つの理由と共感の設計術

「最近の若者、広告を全然見ないよね」——そんな声が企業のマーケティング現場で当たり前のようにささやかれています。
Z世代(1996年〜2012年生まれ)は、生まれたときからスマホとSNSが当たり前のように存在していた“情報リテラシーの高い世代”。彼らは企業からの一方的な広告に対して極めて敏感で、「うさんくさい」「信頼できない」「スキップしたい」と感じているのです。
本記事では、なぜ広告がZ世代に届かないのかを分析し、成功している企業事例から、今後のマーケティングに必要な「共感の設計」について具体的に提案していきます。
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
- Z世代に広告が届かない3つの背景
- Z世代とは?
- データで見る広告不信の実態
- 成功事例|広告ではなく共感で響いた企業たち
- SHEIN|インフルエンサー起用で広告感を薄め「リアル体験」を“自然共有”
- オイシックス|ネガティブも含む正直レビューが“本音共感”を生む
- Adobe × UUUM|使う人が語り手=共創が“自己効力感”を引き出す
- Z世代に届くためのアプローチ設計
- SNSを最大限活用!Z世代に届くインタラクティブなコミュニケーション設計
- 口コミ(UGC)と「信頼できる情報源」を重視するZ世代アプローチ
- Z世代のトレンドを捉え、共感を生むストーリーと文脈を提供する
- LINEやSNSを活用した「紹介導線」の整備で口コミを最大化
- 時代は広告よりも紹介が刺さる
- まとめと今後のマーケティング指針
Z世代に広告が届かない3つの背景
ここでは、Z世代が広告を信頼しなくなった背景にある「意識の変化」や「メディア環境の違い」を概観します。次章以降では、より具体的な行動傾向や信頼構造の変化について掘り下げていきます。
かつて「テレビCMを流せば商品が売れる」時代がありました。しかし今、同じ広告をZ世代に見せても効果はありません。むしろ「うざい」「スキップする」「信用できない」とネガティブな印象を与えることすらあります。
Z世代とは?
Z世代は、一般的に1990年代後半から2010年代前半頃に生まれた世代を指します。彼らは物心ついた頃からインターネットやスマートフォンが存在し、デジタルデバイスやソーシャルメディアが生活に深く浸透している「デジタルネイティブ」世代です。
この世代の主な特徴としては、以下の点が挙げられます。
情報収集能力が高い
幼い頃からインターネットに触れてきたため、膨大な情報の中から必要なものを見つけ出す能力に長けています。また、検索エンジンだけでなく、SNSでの情報収集も得意としています。
多様な価値観を持つ
グローバルな情報に触れる機会が多く、多様性や個性を尊重する傾向が強いです。画一的な価値観に縛られることを嫌い、自分らしさを大切にします。ソーシャルネイティブ: SNSを介したコミュニケーションが当たり前であり、友人やインフルエンサーとのつながりを重視します。情報共有や共感を通じてコミュニティを形成します。
実的で合理的な消費行動
バブル崩壊後の経済状況や社会情勢を見て育っているため、物事を現実的に捉え、コスパやタイパ(タイムパフォーマンス)を重視する傾向があります。
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
Z世代に広告が届かない理由
Z世代の広告離れには、単なる「若者の気まぐれ」ではなく、明確な行動様式の変化があります。
そこには、大きく分けて3つの要因が挙げられます。
日常的に膨大な広告に接することで“広告疲れ”を起こしている
SNSを通じた双方向のやりとりに慣れ、一方通行の広告には反応しなくなっている
発信者の信頼性に強く影響を受ける
これらの背景を理解することで、Z世代に届けるべき“新しいコミュニケーションの形”が見えてきます。
広告疲れと広告を見抜くリテラシーの進化
Z世代は、YouTubeやInstagram、TikTokなどのSNSを中心に生活しており、日常的に数多くの広告やPR投稿に触れています。この環境下で育った彼らは、広告の「演出」や「ステルス性」を高確率で見抜くスキルを自然と身につけています。
さらに2023年10月1日から消費者庁はステルスマーケティングを不当表示として禁止し、2024年6月には初の行政処分が実施。広告であることを隠す行為は、信頼失墜に直結します。(出典:消費者庁)
一方通行のメッセージが嫌われる
Z世代は“対話”を前提とした情報の受け取り方をします。企業が一方的に押し付けるメッセージには関心を示さず、自分も参加できる・巻き込まれる体験にこそ価値を見出します。
総務省の令和5年度調査では、Z世代のSNS利用率は90%超。双方向コミュニケーションの中で得た「自然な声」を信頼し、それが購買につながっています。(出典:総務省)
「誰が言っているか」が信用の決め手
Z世代は「何を言っているか」よりも「誰が言っているか」を重視します。企業広告よりも、友人、SNSインフルエンサー、リアルな使用者の声に耳を傾ける傾向があります。
LINEリサーチ(2025年3月調査)では、Z世代にとって“信頼できる人”からの情報が最重要。ゲームやミーム文化への関心も高く、既存のPR手法では響きにくい傾向があります。(出典:LINEリサーチ)
データで見る広告不信の実態
Z世代にとって、広告はもはや「情報」ではなく「ノイズ」になりつつあります。
広告に対する即時的な拒否反応も顕著です。僕と私と株式会社の調査では「SNSに購買行動を促されたことがある」と回答したZ世代が30.2%いたのに対し、「広告っぽさ」のある投稿を見たとき、「購買意欲が高まる」と答えたのはわずか14.6%にとどまり、逆に「購入意欲が少し下がる」「購入意欲が完全になくなる」と答えたのは43.4%にも及びました。
(出典:僕と私と株式会社Z世代の4割が“広告っぽさ”が強い広告は「購買意欲が下がる」と回答。SNS広告について大調査! )
こうした実態は、企業がZ世代に向けて広告を発信する際、従来型の“押しつけ型メッセージ”ではなく、「自然な流れ」「信頼できる発信者」「共感できる世界観」によるアプローチが求められていることを示唆しています。
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
成功事例|広告ではなく共感で響いた企業たち
Z世代に響いたマーケティング成功事例には、いずれも「企業が語る広告」ではなく、「ユーザー自身が語りたくなる体験設計」という共通点があります。以下に、3つの企業の事例を紹介します。
SHEIN|インフルエンサー起用で広告感を薄め「リアル体験」を“自然共有”

SHEIN
ファッションとライフスタイルのグローバルECブランドで世界150か国以上でサービスを展開しています。日本でもZ世代を中心に利用者の多いサービスとなっています。
SHEINは2023年以降、日本でもフォロワー数千~数万人のナノ・マイクロインフルエンサーを戦略的に起用。
Campaign Japanによれば、「ナノインフルエンサーは非常に親しみやすい存在」として高いエンゲージメントが出るほか、コンバージョン率は約22%に達するという。(出典:campaign japan )
また、東洋経済オンラインの記事では、SHEINが「中小インフルエンサー」を大量起用し、自然なレビュー動画をSNS上に広げていると報告されています(出典:東洋経済ONLINE)
#Sheinhaul のようなUGCが生まれる文化を活かし、「広告らしさ」ではなく「ファッション体験」を自然と伝播させる設計が功を奏しています。
Oisix|ネガティブも含む正直レビューが“本音共感”を生む

Oisix
選りすぐりの食材やミールキット・惣菜など、毎週1500商品以上を販売する宅配サービスです。有機野菜や特別栽培農産物、無添加の加工食品など、安全性に配慮した食材が特徴です。
Oisixは“試してレビュー”のUGCをSNS中心に展開し、2023年夏にはインフルエンサー数を減らしながらも質の深い投稿を維持したと同社広報が明かしています。(出典:Oisix ra daichi)
Shopifyブログでも、同社が#Oisix ハッシュタグを活用し、ユーザー投稿を再シェアする手法で新規顧客獲得に成功していると報告しています。(出典:Shopify)
加えて、FeedForce提供のショート動画制作サービスでは、UGCライクな縦型動画を14日以内に制作し、SNS導線を整備 。
「味の感覚や量感などリアルな体験を語る小さな声が逆に信頼になる」という設計がZ世代に響きました。
Adobe × UUUM|使う人が語り手=共創が“自己効力感”を引き出す
![]()

Adobe
画像編集ソフトのPhotoshopや、ベクターグラフィックソフトのIllustratorなど、クリエイティブ関連のソフトウェアを開発・販売するアメリカの企業です。
UUUM
日本のマルチチャンネルネットワーク(MCN)、YouTuber事務所、並びにレコード会社です。HIKAKINやはじめしゃちょーの影響もあり、Z世代には「YouTuber事務所」としての認知が広いです。
AdobeはUUUMと2022年から共同でコンテストや記念動画を展開し、2023年6月にも10周年MVを公開 。
UUUM noteでも、2023年以降「従来とは違う共創的な取り組み」として注力されていると紹介されています。(出典:UUUM)
UUUM所属のHIKAKIN、はじめしゃちょーら39名がPremiere Proを使って編集し、プロではなく“同世代クリエイター”として語る設計が生きています。(出典:UUUM)
結果は「プロっぽさ」への抵抗感を崩し、「自分にもできそう」という自己効力感を引き出す効果に成功。それがブランドの敷居を下げ、Z世代に訴求しました。
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
Z世代マーケティングの実施ポイント
Z世代に響くマーケティングの本質は、企業の一方的な発信ではなく、ユーザー自身が「語りたくなる」体験を設計することにあります。Z世代の行動様式や情報収集の特性を踏まえ、具体的なマーケティング実施ポイントを解説します。
SNSを最大限活用!Z世代に届くインタラクティブなコミュニケーション設計
デジタルネイティブであるZ世代にとって、SNSは情報収集と日常のコミュニケーションの中心です。単に広告を配信するだけでなく、彼らが積極的に参加し、発信したくなるような双方向の仕掛けを導入することが、Z世代マーケティングでは不可欠です。
ユーザーのエンゲージメントを高めるには、投票機能やクイズ、コメント欄などを活用し、能動的に関われるコンテンツが効果的です。例えばTikTokのハッシュタグチャレンジやInstagramのARフィルターは、Z世代の参加意欲を刺激し、拡散を促します。
ライブ配信やQ&Aセッションでリアルタイムに交流することで、親近感や信頼性を醸成できるでしょう。各SNSの強みとユーザー層を理解し、それぞれに最適なコンテンツを企画することが、Z世代へのリーチを最大化する鍵です。
口コミ(UGC)と「信頼できる情報源」を重視するZ世代アプローチ
Z世代は、企業からの公式メッセージよりも、友人、インフルエンサー、そして一般ユーザーが発信する「リアルな口コミ」に最も高い信頼を置きます。この特性をZ世代マーケティング戦略の中心に据えることが、成果に直結します。
ユーザーが自ら商品やサービスについてSNS投稿したくなるようなインセンティブ設計や魅力的な企画を検討しましょう。オリジナルのハッシュタグ提供や公式アカウントでのユーザー投稿紹介は、自然な形でUGCマーケティングを促進し、Z世代の購買行動を後押しします。
インフルエンサー選定では、フォロワー数より親和性やエンゲージメント率を重視し、飾らない日常を発信するナノ・マイクロインフルエンサーは、高い訴求力とコンバージョン率が期待できます。正直なフィードバックも積極的に受け入れ、適切に対応することで、ブランドへの信頼性はさらに高まります。
Z世代のトレンドを捉え、共感を生むストーリーと文脈を提供する
流行に敏感で、社会課題や多様性への関心が高いZ世代には、彼らの価値観やライフスタイルに深く寄り添ったコンテンツが響きます。
ブランドへの好意を醸成し、長期的な関係を築くためには、共感性が不可欠です。Z世代が日常的に抱える課題や大切にする価値観(環境意識、自己表現、多様性など)と親和性のあるストーリーをキャンペーンの核に据え、「私のためのブランドだ」と彼らが感じられるような、パーソナライズされた体験を提供することが重要です。
一方的な情報提供ではなく、ユーザーが商品やサービスの開発・改善に参加できる機会を提供することで、ブランドへのエンゲージメントが高まり、ファン化を促進します。SNSのミームや流行をブランドメッセージと自然に融合させることも効果的ですが、ブランドイメージとの整合性に注意が必要です。
LINEやSNSを活用した「紹介導線」の整備で口コミを最大化
Z世代の購買行動において、「人からの紹介」は非常に大きな影響力を持っています。
友人や信頼できる人からの情報は、広告よりもはるかに高い購買意欲に結びつきやすい傾向があるため、紹介導線の整備は必須です。友人を紹介した側・された側の双方に魅力的なメリットがある紹介プログラムを設計し、新規顧客獲得と既存顧客のロイヤルティ向上に貢献させましょう。
限定特典や割引クーポンなどが効果的です。商品購入後やサービス利用後に、簡単にSNSで体験をシェアできるボタン設置やハッシュタグ自動生成機能で、自然な口コミの拡散を促し、オーガニックリーチを拡大できます。
商品やサービス自体が、友人やフォロワーに「話したい」「見せたい」と思わせるようなユニークな価値や感動的な体験を提供できるかが、Z世代の口コミを発生させる最重要ポイントとなります。
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
時代は広告よりも「紹介」が刺さる
今日のデジタル社会において、Z世代の消費行動は従来の広告モデルから大きく変化しています。彼らはSNSを通じて常に新しい情報をキャッチアップしており、企業が発信する一方的な広告メッセージに対しては、強い警戒心や不信感を抱く傾向があります。この背景には、彼らが幼少期からインターネットに囲まれ、情報過多の環境で育ったことが挙げられます。彼らにとって、信頼できる情報源は企業広告ではなく、友人・知人からの紹介や、共感できるインフルエンサー、あるいは一般ユーザーが投稿するリアルな口コミ(UGC)なのです。
購買を検討する際、Z世代はまずSNSで商品やサービスに関する「生の声」を探し、その評価や体験談を重視します。例えば、InstagramのストーリーズやTikTokのショート動画で友人が紹介した商品、信頼するインフルエンサーが「本当に良い」と語るアイテムには、広告では決して得られない「共感」と「信頼性」が宿ります。
このような「紹介」は、広告のように押し付けがましくなく、自然な形で彼らのニーズに合致するため、購買意欲を強く刺激します。企業は、従来の広告戦略から脱却し、いかにしてユーザーが自発的に紹介したくなるような「共感の輪」を作り出すかに注力すべきです。ユーザー間の対話や共有を促すことで、Z世代の心に深く響くブランド体験を提供し、持続的なファンベースを構築することが可能になります。
トピック: 紹介の基本, マーケティングノウハウ
もっとも読まれている記事
2020.05.27 Hiroo Fujii
お友達紹介キャンペーンをしっかり強化すべき理由
2019.04.01 Hiroo Fujii
累計750,000の紹介を誘発するリファラルマーケツールとは?
大事なポイントはリファラルコミュニケーションのデザイン。オンラインだけでなくオフラインも最適化することで紹介経由の顧客獲得が4倍に。 詳しくはこちら>>2020.05.29 Mio Tomiyori

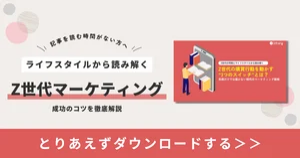


.webp?width=1000&height=667&name=image%20(21).webp)
.webp?width=863&height=512&name=invybanner%20(2).webp)

