2025.07.09 紹介の基本 マーケティングノウハウ
【Z世代マーケティング】購買を動かすのは「友達の紹介」──信頼ピラミッドと成功事例で解説

Z世代の消費行動は、従来のマーケティング手法では捉えきれないほど複雑かつ独特な進化を遂げています。デジタルネイティブとして育った彼らにとって、一方的な「広告」はもはや情報源ではなく「売り込み」と認識され、忌避される傾向が顕著です。
Z世代は何を信じ、何を判断基準として行動しているのでしょうか?
その答えの一つが、「友達の紹介」です。
本記事では、Z世代の消費行動を深く掘り下げ、彼らの「情報の信頼ピラッド」や「友達の紹介」がもたらす影響力について解説します。さらに、企業がZ世代の「本当の信頼」を得て、商品やサービスを「語られる存在」にするための具体的なアプローチを探ります。
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
過去のZ世代マーケティングの記事を読む
>>『Z世代マーケティングの新常識:広告が刺さらない3つの理由と共感の設計術』
Z世代が重視する「情報の信頼ピラミッド」とは?
Z世代が情報に触れる際、彼らにとって重要なのは情報の「量」ではなく、「誰が発信している情報か」という点です。
彼らは日頃から膨大な量の広告や情報にさらされており、その中から「信頼できる情報」を厳しく選別する能力に長けています。
この選別の結果として形成されているのが、「情報の信頼ピラミッド」です。

広告・企業発信:信頼ピラミッドの最下層
信頼ピラミッドの最下層に位置するのが、広告や企業からの直接的な情報発信です。
Z世代にとって広告は「企業目線の売り込み情報」であり、基本的には疑ってかかる対象となります。これは、彼らが幼少期からインターネットに触れ、広告の意図を自然と見抜くリテラシーを身につけているためです。
インフルエンサー・著名人:信頼性と見極めが求められる層
その上に位置するのが、インフルエンサーや著名人からの情報です。
共感性や個人の発信であることから一定の信頼はありますが、「案件っぽい」「PR色(企業からの依頼)が強い」と見なされると、瞬時に信頼度が低下します。彼らはインフルエンサーが発信する情報の裏にある意図を冷静に見極めています。
友達からの紹介:信頼ピラミッドの頂点
そして最上位に位置するのが、「友達からの紹介」です。
金銭的な利害関係がなく、等身大で共感できる存在からのリアルな体験談やおすすめは、Z世代にとって最も純度の高い情報源となります。
このピラミッド構造を深く理解することは、Z世代に対するマーケティング戦略を立案する上での揺るぎない第一歩となります。彼らの情報信頼の基準が「親しい人からの共有体験」にあることを認識することが重要です。
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
Z世代に“友達の紹介”が最も響く科学的根拠
Z世代が「友達の紹介」を最も信頼する理由は、単なる関係性の近さだけではありません。行動経済学や心理学の観点からも、この傾向には明確な裏付けがあります。
行動経済学が示す「紹介」の影響力
行動経済学における定説として、「人は、自分と似た立場や経験を持つ他者の意見に最も影響される」というものがあります。特にZ世代は、「自分で調べて、納得して買う」というプロセスを重視しますが、その過程で「判断のきっかけ」として友人の発言が強く作用します。これは「社会的証明」や「同調行動」といった心理現象が背景にあります。
SNS上で商品やサービスが「バズる」現象も、多くの場合、信頼する「身近な誰か」が発信源となっています。Z世代は、その発信が企業によるプロモーションなのか、それとも信頼できる友人のリアルな「体験談」なのかを瞬時に見極める能力に長けています。
エビデンスから見る「紹介」の絶大な効果
Z世代の購買行動において、「紹介」の影響力は統計データにも明確に表れています。
株式会社PRIZMAが2025年3月に実施した「Z世代の消費行動に関する調査2025²」(※1)によると、商品やサービスに「興味を持つきっかけとなる情報源」として「友人や家族からの情報・意見」(38.0%)が「SNSの投稿やレビュー」(37.3%)と並んで高い割合を示しています。また、購入時に参考にする情報源としても同様に高い割合を占めています。
これらのデータから、信頼できる実体験に基づいた紹介、特に身近な人からの情報はZ世代の心を強く動かすことが裏付けられます。Z世代マーケティングにおいては、「紹介される理由」と「紹介する理由」が一致するような設計が、極めて効果的と言えるでしょう。
(※1)出典元: PR TIMES株式会社PRIZMA「Z世代の消費行動に関する調査2025」 (2025年3月18日発表)
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
“バズ”と“紹介”は似て非なるもの
SNS上で何かが爆発的に拡散される現象を「バズ」と呼びます。一方、友達から自然におすすめされる体験は「紹介」です。一見似たような拡散現象ですが、この2つは根本的に異なる性質を持っています。
バズは“話題性”、紹介は“信頼性”
「バズ」は、多くの場合、“目新しさ”や“面白さ”といった話題性によって引き起こされる一過性の現象です。例えば、期間限定の新しいスイーツや話題のイベントは「試してみたい」という衝動に駆られますが、「誰かに心から伝えたい」とまでは思わないことも少なくありません。
一方で、「紹介」は“信頼”を前提とした行動です。紹介者が「これは、あなたにもきっと合うはず」と感じるパーソナルな動機に基づいており、受け手もそれを「自分ごと」として捉えやすくなります。紹介は、単なる情報の伝達ではなく、信頼関係に基づく「おすすめ」の行動と言えます。
「共感消費」と「紹介」の違い
「共感消費」とは、Z世代が自身の価値観や社会問題への意識と合致する商品やサービスを選ぶ消費行動です。「共感消費」は“価値観の共有”が起点となり、ファッションやコスメのように「私もそれが好き」という共通の感覚から広がる傾向があります。
「紹介」とは、信頼する友人や知人からの直接的な推奨によって商品やサービスを知り、購買に至る行動です。本記事で取り上げる「紹介」は“信頼”を起点とし、「あの人が勧めるなら間違いないだろう」という「保証」の役割を果たします。
バズは瞬間的な熱狂を生む可能性がある一方で、紹介は長期的な信頼関係を構築します。企業がどちらを目指すかによって、設計すべきマーケティング戦略は全く異なるのです。
Z世代の「共感消費」の詳細については、『Z世代はなぜ流行に飛びつく?』で深く掘り下げています。
>>『Z世代はなぜ流行に飛びつく?SNS時代の“共感消費”の正体』を読む
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
自然な「紹介」が生まれやすいサービスの特徴
Z世代にとって「紹介したくなる」サービスとは、単に便利だったり流行っているだけでは不十分です。彼らが自発的に友人に話したくなるのは、「体験して本当に良かったから、この感動を共有したい」と思えるような設計がなされているサービスです。
「語りたくなる構造」を持つか?
ユーザーが「思わず人に話したくなる」ような体験を最初の段階で提供できているか、が重要です。例えば、
- 使ってすぐに驚きをもたらすようなUI(ユーザーインターフェース)デザイン
- ユーザーの期待を超える意外性のあるサービス内容
- 友人にも使ってほしくなるようなインセンティブ設計
こうした「語りたくなる要素」がサービス内に仕込まれていると、それが紹介の起点になりやすい傾向があります。
また、Z世代は「これは私の価値観に合っている」「私のライフスタイルにフィットしている」と感じたときに、それを誰かと共有したいという心理が強く働きます。つまり、機能的な価値だけでなく、「共感価値」やサービスが提供する「世界観への没入感」が重要なファクターとなります。
紹介の障壁が“限りなくゼロ”であること
加えて、紹介行動のハードルが低く設計されているかどうかも極めて重要です。例えば、「LINEで1クリック送信」「URLをタップしてシェア」など、紹介の導線がスムーズに設計されているサービスは、Z世代の間でも自然に広がります。
一方で、重たいフォーム登録が必要だったり、複雑な手順を踏まなければ紹介できないような設計では、それだけで「誰かに紹介する気」が削がれてしまいます。Z世代マーケティングにおいては、プロダクトの構造自体に「紹介されやすさ」を織り込むことが不可欠です。
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
成功事例に学ぶ、Z世代を動かす「紹介設計」
では実際に、Z世代の行動様式を捉え、「紹介」を巧みに設計した成功事例をいくつか見ていきましょう。
ルシアクリニック:紹介の“安心感”が、来院の一歩を後押し

美容医療を提供するルシアクリニックでは、invyを導入し、LINEを活用した紹介キャンペーンを実施しています。紹介者にも被紹介者にも特典がある「相互インセンティブ型」の設計がなされており、Z世代の間では「安心できる相手に勧められたから行ってみよう」という動機が多く見られます。
美容医療という慎重になりやすいジャンルにおいて、信頼できる友人の言葉が背中を押す決定打になる──この構造がうまく活用されており、キャンペーン導入後には紹介経由の来院数・契約率がともに上昇しました。
「誰かに教えたい体験」と「勧めやすい設計」が揃っていることが、Z世代の紹介を自然発生させる鍵となっています。
\他の企業のinvy導入事例を読む/
Netflix:友達と「一緒に観たい」が動機を後押し

動画配信サービスのNetflixは、新規ユーザー獲得のために「紹介コードで1ヶ月無料」といったキャンペーンを定期的に実施しています。Z世代の間では、「一緒にこの作品を観たい」「話題の作品を共有したい」という動機付けと、「無料になる」というお得感がうまく融合されています。これにより、友人との会話の中で自然に紹介コードがシェアされる仕組みが機能しています。
TikTok:インセンティブと「同調圧力」が相乗効果を生む

ショート動画プラットフォームのTikTokは、招待した友人がアプリをインストールするとポイントが貯まる仕組みを導入しました。このポイントは現金やギフト券と交換できるため、「お得だから友達にも広めたい」という明確な動機が発生します。
さらに、「TikTokやってないの!?」というZ世代特有の「同調圧力」も相まって、短期間で爆発的なユーザー獲得と拡散に成功しました。これは、物質的なインセンティブとソーシャルな動機付けが巧みに組み合わされた成功例と言えるでしょう。
スターバックス:気軽な「eギフト文化」が紹介行動を促す

スターバックスのドリンクチケットをLINEで簡単に送れる「eギフト」は、Z世代にとって「カジュアルなプレゼント」として完全に定着しています。これは、直接的な紹介インセンティブとは異なりますが、「私が好きなものをあなたにも知ってほしい」という自然な「紹介心理」を後押しする好例です。
気負わずに贈れる「カジュアルギフト」という設計が、Z世代の友人間のコミュニケーションと紹介行動にマッチし、新たな文化を生み出しました。
これらの成功事例に共通するのは、紹介されることが「気まずくない」「ちょっと得する」「誰かと共有できる楽しい体験」になっている点です。紹介行動を自然に「選択肢の一つ」としてユーザーの行動に組み込んでいる設計こそが、Z世代へのマーケティング成功の鍵となります。
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
Z世代マーケティングの本質は、「語らせる」デザインにあり
デジタルネイティブのZ世代は、広告を避け、「友達の紹介」を最も信頼します。「情報の信頼ピラミッド」が示すように、企業広告やインフルエンサーより、親しい友人のリアルな体験談が彼らの行動を動かす力を持つのです。
SNSでの「バズ」が話題性を追求する一時的な現象である一方、「紹介」は信頼性に基づくパーソナルな「おすすめ」であり、長期的な関係を築きます。Z世代の「共感消費」が価値観の共有から広がるのに対し、「紹介」は「あの人が勧めるなら間違いない」という保証の役割を果たします。
Z世代の信頼を得るには、商品やサービス自体が「語りたくなる設計」を持つことが不可欠です。驚きのある体験や、紹介の障壁が低い設計が重要となります。ルシアクリニックやNetflixなどの成功事例は、この「紹介設計」の有効性を示しています。
Z世代マーケティングの本質は、「何を伝えるか」ではなく、「どう語らせるか」という視点にあります。「友達の紹介」を起点に、自然で持続的なブランド接点を作り出すことが、Z世代を動かす鍵となるでしょう。
invyが支援する“語られる仕組み”の設計
そうした“語りたくなる設計”を実現する手段のひとつが、リファラルマーケティングの活用です。
リファラルマーケティングクラウド「invy」は、紹介の設計・管理・効果測定までを一貫して支援するため、LINEやSNSを活用した自然な紹介導線の構築や、紹介を後押しするインセンティブ設計、ユーザーごとの紹介状況の可視化など、紹介が“語られる”までの仕組みを柔軟に設計可能です。
信頼の最上位にある「友達の紹介」をマーケティングの起点に据えることで、Z世代とのより自然で持続的なブランド接点が生まれるはずです。invyは、その起点づくりを支援する、これからの時代のマーケティングパートナーです。
\Z世代マーケティングのコツを徹底解説/
過去のZ世代マーケティングの記事を読む↓
>>『Z世代マーケティングの新常識:広告が刺さらない3つの理由と共感の設計術』
>>『Z世代はなぜ流行に飛びつく?SNS時代の“共感消費”の正体
>>『Z世代とインフルエンサーの本当の関係性とは? ─ フォロワー数より「共感」が信用される時代へ』
トピック: 紹介の基本, マーケティングノウハウ
もっとも読まれている記事
2020.05.27 Hiroo Fujii
お友達紹介キャンペーンをしっかり強化すべき理由
2019.04.01 Hiroo Fujii
累計750,000の紹介を誘発するリファラルマーケツールとは?
大事なポイントはリファラルコミュニケーションのデザイン。オンラインだけでなくオフラインも最適化することで紹介経由の顧客獲得が4倍に。 詳しくはこちら>>2020.05.29 Mio Tomiyori

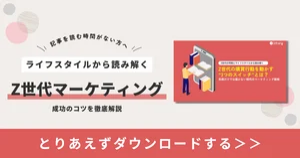



.webp?width=1000&height=667&name=image%20(21).webp)
.webp?width=863&height=512&name=invybanner%20(2).webp)

